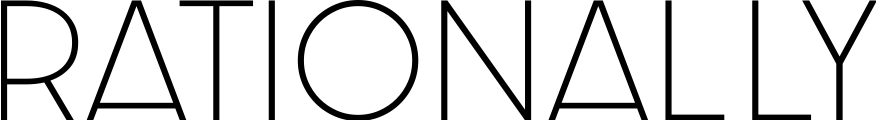スポットライト – Logicool Spotlight

3月9日に発表され、各種メディアで記事が書かれている新型のプレゼンター、それが Spotlight だ。Windows、macOS に対応している。
レーザーポインターではなく、ソフトウェアでポインタを実装している。ジャイロセンサーによる制御なので、自在な動きにポインタが追随できる。ソフトウェアポインタなので、マルチスクリーンやマルチモニタでのプレゼンでもすべてにポインタが表示される。スライド送りももちろんできる。
詳細については、Logicool 社のサイトをご覧いただきたい。
Spotlightを体験してください。焦点領域を強調表示/拡大してディテールを示すことができる、高度なポインターシステム…
驚異的なのは、1分の充電で3時間稼働すること。フル充電で3ヶ月持つとのことだ。実際に1分充電にて、1時間の講演が余裕で行えた。
アップルストアでは、すでに販売されている。色は、Apple 限定のシルバーだ(アップルストア以外でシルバーが売っているようだが値段からして….。シルバーが欲しい場合はアップルストアを見ることをおすすめする)。
ゴールドとスレートカラーについては、発売日を待つ必要がある。Amazon では予約を受け付けている。
開封の儀

見ての通り、おしゃれなパッケージである。アップルストアで入手したが、他のアップル製品やサードパーティ製品と見比べても見劣りしない。秀逸である。

では開封してみよう。

さっそく Spotlight 本体を拝むことができる。本体に USBレシーバーが差し込まれた状態となっている。持ち運びも便利であり、USB レシーバーをなくす心配も軽減できる設計だ。
Spotlight 本体は、実にシンプル。3つのボタンしかない。
一番上(写真では、一番左、以下同様に)がポインタ用のボタンだ。真ん中は一番よく使うであろう次へ進むボタン。一番下が、戻るボタンだ。スライド操作とポインタ操作が行えるわけだ。

箱内は三重構造となっている。本体が収納されているしきりを外すとそこには、USB ケーブルがある(写真は、収納されていたケーブルを取り外した状態になっている)。ケーブルは、USB タイプ A と USB タイプ C のコネクタ構造である。これは充電用のものだ。
Spotlight は、USB-C で接続し、PC や充電器側は、USB-A で接続することで充電を行う。
右端は、Logi のロゴをあしらった持ち運びに便利な入れ物だ。Spotlight 本体がスッポリと収まるベストサイズだ。

本体から USB レシーバーを抜き出したところだ。指でつまんで抜き出すことができる。これを PC に接続すれば即利用可能となる(※専用のドライバ・ソフトウェアが必要、後述)。

USB レシーバーを外した奥には、USB-C の口がある。ここに前述のケーブルの USB-C のオス側を接続するわけだ。実にスマートなデザインである。

Spotlight に充電ケーブルを接続したところ。USB-A 側を PC や充電器に接続すれば充電できる。
実践の儀
さて、私は、Spotlight を入手し、即、スクーの生放送授業で使用した。ここからは、使用までの準備と実際に使って見た所感を残そう。
準備
まず、Spotlight を使うためには、専用のドライバ、ソフトウェアをインストールする必要がある。これは、Logicool 社のサイトからダウンロードできる(同梱はされていない)。
入手先 URL は、Spotlight を箱から取り出した際に記載がある。ここでは、リダイレクトされた後の URL を残しておこう。
私は、macOS を使っているので、ここからは MacBook Pro (OS は、macOS Sierra 10.12.3)でのセットアップを見ていく。

ダウンロードしたら他のアプリ同様にインストールしていく。そう、ダブルクリックだ。直感でいける。



次第にテーマカラーのサークルが大きくなっていくアニメーションになっている。最後は。

インストールが終了すると、そのまま「ツアー」が開始される。これは、単に製品や操作の紹介が行われるだけではなく、セットアップを導いてくれる。


USB レシーバーを本体から取り外し、充電ケーブルを接続するよう促される。

ここで、1分充電(3時間利用可能になる)が実施される。

1分間の進捗をアニメーションとパーセンテージで知らせてくれつつ、TIPS が表示される。フル充電で最長3ヶ月ももつ。

デバイスの電源ON/OFFが不要。というか、そもそもそういうスイッチやボタンがない。自動制御だ。


USB レシーバーを PC に接続すれば、即利用可能になる。Bluethooth 接続したい場合は、右下の文章をクリックすると切り替えることができる。

私の環境では、Bluetooth での接続がうまくいかなかった。一旦この専用ソフトウェアを終了させて、macOS の Bluetooth 接続でペアリングすることで接続することができた。ただ、動作がもっさりしており、感度がよろしくない感じとなった。この辺りは使用しながら様子を見てみたいと思う。

接続が完了すると操作方法のガイダンスに切り替わる。全画面表示となりガイドされる。


ウリでもあるスポットライト機能でチュートリアルは進む。マウスクリックも可能だ(不可にもできる)。
ポインタは、スポットライトの他にも拡大モード、ポインタモードが選択できる。

つぎのチュートリアルは、プレゼンタイマーだ。Spotlight には、時間経過とともに、本体をバイブレーションさせる機能が搭載されている。時間は、アプリで設定可能だ(後述)。

実際にこの段階で本体がブルブルする。


あとは使うのみ!使うべし!
では、アプリでの設定を見ていこう。

タイマー、ポインタ、次へ、戻るのそれぞれに設定をすることができる。

「クロック」とは、プレゼン画面にタイマーを表示する機能だ。あとは、指定した時間経過でブルブルしてくれる。

「強調表示」とは、要はスポットライトのことだ。ポインタの周囲だけにスポットライトが当たったような効果にしてくれる(ポインタ周辺以外が暗くなる)。スポットライトの大きさとマウスカーソルの表示/非表示が選択できる(マウスカーソルモードだとクリックすることができる)。
「拡大」は、ポインタの周囲を拡大表示してくれる機能だ。拡大する範囲を細かく指定できる。マウスカーソルも上述のように設定できる。
「円」は、ポインターモードだ。白丸を表示してくれる。また、その周囲に白い枠の丸を描いてくれる。この白い枠の丸の大きさを設定できる。マウスカーソルモードにすると白丸が中心ではなく、マウスカーソルになる。

進むボタンを押し続けたときの動作を設定できる。

戻るボタンを押し続けたときの動作を設定できる。
カスタム キーストロークを有効にするには、OS のアクセシビリティで Spotlight のアプリに許可を与えておく必要がある。

詳細設定で、ポインタの速度など設定できる。既定では私的にはちょっと動作が遅く感じたので調整を行なった。

バイブレーションの強度も設定できる。いざというときにびっくりしない優しい設定にしよう。

USB か、Bluetooth かの接続設定も切り替え可能。
実践
入手して約1時間後にさっそく使ってみた。しかも、スクーの生放送でだ。

Schoo のロゴのあたりにポインタがある場合のスポットライト。白地の背景だが、スポットライトが当たっていないところは暗くなる。

生放送には、ポインタモードで臨んだ。スタジオには、自分の PC のほか、モニターにもスライド投影されているが、すべてにポインタが表示される。もちろん、写真のように自分の PC にむけてポインタ操作をしてもいいし、モニターにむけてポイント操作してもいい(生放送では、モニターにむけて操作した)。そもそもジャイロセンサーで制御しているので、PC や モニターに向ける必要すらないのではあるが。

スクーでの生放送の恒例となっている記念写真でも、なぜか Spotlight 推しにw
右側は MC (受講生代表) を務めてくださった江川みどりさん。
この放送は、現在「公開準備中」公開されると会員向けにご覧いただける。Spotlight の使用感も体感いただけるだろう。
【講師:長沢 智治先生】▪︎授業概要 ・プロジェクトマネジメント ・統制型プロジェクトマネジメント ・自律型プロジェクト…